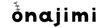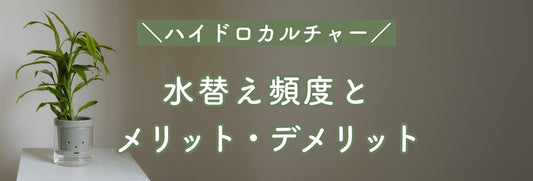ガーデニングや鉢植えよりももっと簡単に植物を育てられる水耕栽培。
まだまだ寒い時期ですが、ガラス越しに観察できる根からは春に向かって成長する姿を感じることができますし、春には彩り豊かな花と生命力あふれる緑がお部屋にあふれます。
春への期待が膨らむこの時期、球根とおしゃれな球根ベースで春へのカウントダウンをしてよう!と意気込んだはいいけれど、いざ調べてみると、スタートするのは秋がおすすめと書かれている…
今からでは今年の春にはもう間に合わない???と、せっかくの気持ちがしょんぼりしてしまった方はぜひこの記事を読んでみてください。
秋に始めるのがおすすめと言われる理由

春に咲く花の球根を「秋植え球根」と言います。土で球根を育てる場合、春にきれいな花を咲かせるには、秋のうちに植え、土の中で冬の寒さを経験させなければいけません。寒い冬を経て、球根たちは春にきれいな花を咲かせるのです。
これは土で育てる場合の話ですが、水耕栽培でも同じです。9~11月のうちに出回っている「秋植え球根」を買ってきて、水耕栽培の場合は、土の中で冬を越す代わりに、冷蔵庫で約1か月冬を経験させる「春化処理」を行います。
水耕栽培を始めるには10~12月頃が適期だと言われているのはこのためです。
秋から備えておかなければそもそも球根が手に入らないということですね。
2月から始めるメリット、デメリット

ただ、毎年球根を育てている人はそのスケジュールに慣れてしまっているかもしれませんが、春を目前に初めてチャレンジしてみようと思い立った方には、何ヵ月も前から球根の準備が必要だったと言われても、がっかりですよね…
でも、おすすめの時期を逃したからと言ってあきらめる必要はありません!
2月からでもまだ間に合いますし、なんと2月から始めることのメリットすらもあるのです。
ここからは、水耕栽培を2月から始めるメリット・デメリットについて紹介していきます。
メリット
1~2月は、お花屋さんや園芸店に根や芽が少し出てきた「芽出し球根」が並び始める季節なのです。
「芽出し球根」とは文字通りすでに芽が出ている球根のことで、秋にポット苗に植え付ける作業をすでに生産者さんが行ってくれています。球根の中には傷がついていたり、球根そのものの不良で、どんなに上手に育てても芽が出ないものもないとは言えません。
芽出し球根なら、確実に芽が出ている球根を入手できるので、初めて水耕栽培にチャレンジする方にはこの季節がぴったりなのです!
中には花芽がついているものもあり、こちらを使えば、芽は出たけれどうまく花が咲かなかったという心配もいりません。
また、10~12月から始めるよりも、室内の温かい部屋で過ごす期間が短くなるので、花が大きくなりすぎず、球根ベースとのバランスがとれるメリットも!
デメリット
2月になると、もう芽や根の出ていない球根は手に入らないので、球根を一から育てて、根が伸びていく様子を観察したり、芽が出る喜びを味わったりと水耕栽培で日々の成長を楽しみたかった方には残念ながら今年は間に合いません。
秋から育てるよりは長い期間楽しめないので少し寂しくはありますが、きれいな花を室内で堪能できる水耕栽培の魅力にとりつかれた方はぜひ、来年は秋から準備してみてください。
ポット苗から始める水耕栽培

ポット苗とは、ホームセンターや園芸店などで見かけるビニールポットで育てられた苗のことですが、種子植物だけでなく球根の苗もあります。
先ほども述べたとおり、ポット苗の球根なら2月からでも手に入るので、今回はこちらを使って水耕栽培にチャレンジしてみます。
水耕栽培の手順

1.ポット苗の状態の芽出し球根を購入する
2.ポットからそっと外して、土を優しく落とす
この段階では無理やりとろうとせず、土がだいたいとれればOK。
3.根についている土を流水で洗い流す
なるべく根っこが切れないように注意が必要ですが、少しくらいは大丈夫です。
最後に水を張ったバケツの中でゆするようにして、細かい土をきれいに取り除きましょう。土が残っていると水が濁ったり腐ったりの原因になります。
4.花瓶に水を入れる

水は根っこの3分の1が水につかるくらいまで入れる。球根は腐りやすいので、根が短い時は水につからないよう注意してください。
5.日当たりのいいところに置く

水耕栽培の基本的なやり方や花瓶の選び方、初心者におすすめの球根は、「初めての球根の水耕栽培 おすすめの種類と球根ベース花瓶10選」のコラムでも触れています。そちらも併せてお読みください。
水耕栽培が終わったら?来年も咲かさるために
水耕栽培では基本、その年の開花は一度きり。一度咲いた球根は捨ててしまう方もいるのですが、1年で終わらせのるはもったいないと思った方、ひと手間加えて庭や鉢に球根を植え替えると、もしかしたら来年も花が楽しめるかもしれません。
翌年の開花にチャレンジしてみたい方は、次のような手順で球根の管理をしてみてください。
1.花がらを摘む
花が咲ききって、水分が抜けてしわしわと枯れてきたら終わりのサイン。花がらを手で摘み取ります。(花茎ごとカットする方もいますが、断面から細菌が入る可能性もあります)
※葉っぱは光合成に必要なのでそのままにしておきます。
2.土に植える
葉が緑のうちに植木鉢に植えて日当たりの良い場所に置くか、日当たりの良いお庭や花壇に地植えします。深さはちょうど球根が隠れて葉の根元が土に触れるぐらい。
3.水と肥料を与える
水耕栽培でした球根は土で育てるよりもより多くの養分を使っているので、スカスカになった球根に栄養を与えてあげましょう。
※水は土が乾いてきたらあげる程度で、水のあげすぎには注意。雨のあたるところであれば、植え付け時に水をあげたらあとは雨にまかせるぐらいでOK。
4.葉っぱが黄色く枯れるまで普通の植物と同じように育てる
梅雨前に葉っぱが黄色く枯れてくるので、球根を掘り起こします。この時、根を痛めないよう注意してください。
5.球根を乾燥させて秋まで保管
掘り起こした球根の土を落としたら、日陰で1週間ぐらい乾燥させます。その後はネットなどに入れて、風通しがよく涼しいところで秋まで保管しましょう。
6.秋がきたら土に植える
水耕栽培で一度開花した球根は、もう一度水耕栽培では育てることができません。球根の養分を使い切っているからです。必ず鉢植えやお庭などの養分のある土に植え込みしてあげましょう。
もう一度花を咲かせる可能性のある球根。その生命力はすごいですね。おうちの中で毎日見ていて、愛着のわいたかわいい球根。もう一度花を咲かせてあげたいと思った方は、少し手間はかかりますが、来年の開花にチャレンジしてみてください!
ポット苗からの水耕栽培におすすめ花瓶10
ポット苗の球根を使う場合根がもうしっかりついているものが多いので、根の長さによっておすすめの花瓶が違ったり、くびれ部分が細すぎるものではあとから花瓶に入れるのが難しかったりもします。その点を踏まえて、おすすめの花瓶を紹介していきます。
根が伸びていてもOK、球根をポンと乗せられる花瓶
1.ラッパ型球根ベース

ポットの根が長く伸びていても、安心の高さです。ヒヤシンスやチューリップはLサイズ、ムスカリやクロッカスはMサイズ、と球根のサイズによって選べるのも◎
2.キュっとくびれ小瓶

ヒヤシンスのような大き目の球根にはぴったり。高さもくびれの内寸的にも、ポット苗ですくすく育った球根も十分受け止めてくれるサイズです。
3.くびれ小瓶

小ぶりですが、くびれ部分がそんなに細くないので、ポット苗から取り出した球根も大丈夫。室内のどこにおいても良いサイズです。
4.こなゆきさん

冬にぴったりのまっしろなこなゆきさん。ムスカリやクロッカスのような小ぶりの球根を、ちょこんと乗せるととてもかわいいです。ひんやりとした印象も水耕栽培にぴったり。
生えていた根っこの広がりを気にせず入れ替えられる筒状の花瓶
5.こしたかさん

底部分も広く、高さもしっかりあるので、スイセンやチューリップの球根におすすめ。根も窮屈になりすぎないスペースがあります。
6.つつさん

つつさんに球根をいれると、ビーカーで育てているようなかわいさがあります。シンプルだからこそ、球根のユニークさが際立つ花瓶です。
7.電球さん

ガラス花瓶にワンポイントが欲しい方におすすめの電球さん。ナチュラルな三本の紐は自然を感じさせる球根植物にはぴったり。底部分が丸く太った形も、根にとっては心地よい広さです。
8.ダイヤベース

根っこの観察を楽しむには不向きですが、ポット苗からの水耕栽培はお花が主役。お花を上品に引きたててくれる、足つきの形とダイヤ柄が特徴の花瓶です。
水耕栽培ならではのアレンジを楽しむ花瓶
9.ジェミニ

浅くて細長い形のジェミニには、ぜひムスカリやクロッカスなどの小さい球根を横並びで並べて。水耕栽培は透明のガラス花瓶が多いですが、きれいな色のお花が多いので白やシルバーの花瓶ともよく合います。
10.メダカ鉢

水耕栽培と好相性なメダカ鉢。いくつかの球根や苔、石などを組み合わせてアクアリウムやテラリウム風にアレンジしても楽しめます。自由な発想で水耕栽培してみてください。
いろんな花瓶を見ていると、水耕栽培にチャレンジしてみたくなってきますね。水耕栽培は誰でもできる簡単な方法で、室内に春を感じられる方法です。やってみたいと思った時が始め時!
今からでもまだ十分間に合いますので、今年の春はきれいなお花とその香りに包まれながら迎えてみませんか?
onajimiでは、オリジナルの花瓶や鉢、海外でセレクトをしたおしゃれなフラワーベースなど、お手頃価格にて種類豊富にご用意しております。